避難所では、子どもと周囲の問題でお伝えしたように、子どもの騒ぐ音や泣き声は親も周囲も気になるところです。子どもは大人以上に不安や恐怖を抱えていますが、その表現方法や発散方法が分かりません。
少しでも地震から子どもの気を逸らすために、遊び道具やおもちゃを避難グッズの一つとして備えてみるのもおすすめです。小さな事かもしれませんが、震災・避難生活でのストレスの軽減につなげてあげましょう。
Contents
避難時におもちゃを選ぶポイント

大好きなおもちゃを持って行ってあげたい!というのが親心ですよね。しかし、生活をする上で必要な避難グッズはたくさんあります。(例:【一次持ち出し】防災グッズリスト)
そのため、以下の3つのポイントを押さえて遊び道具やおもちゃを選び、持ち出しましょう。
大き過ぎず、かさばらないもの
お気に入りのおもちゃでも、あまりに大きすぎると防災リュックに入りませんし、他の物を減らさざるをえません。そのため、かさばらないものを選ぶ必要があります。
もし、このおもちゃやぬいぐるみがないと子どもが不安になる、という場合は子どもの防災リュックに入れてもいいとは思います。
どうしても必要という場合には揺れがおさまって、建物の倒壊の可能性を確認(素人判断にはなりますが)してから取りに戻りましょう。困難な時は「おうちが直ったら取りに行こうね」とひたすら言い聞かせるしかありません。
音が出ない(イヤホンが使える)もの
避難所では色んな方が生活しています。特に、高齢な方や病気を患っている方、ストレスや恐怖で疲れ切っている方にとっては、おもちゃやゲームの音を不快に感じてしまうかもしれません。
子どもがすることだから、気にせず見守ってほしいという意見もあるかもしれません。しかし普段なら気にならないことも、慣れない避難生活で余裕を持てない場合もあります。実際にはなかなか難しいのですが、できる限り子どもも周囲もお互いが譲りあう心が大切です。
どうしても音がなるおもちゃの場合はイヤホンを付けられるか確認しましょう。特に最近のゲーム(持ち運べるタイプ)は、イヤホンジャックがあります。避難グッズとして持ち出す場合は、かならずイヤホンも入れておきましょう。
みんなで遊べるもの
みんなで遊べる、というのは絶対必要な条件ではないのですが、子どもたちは、誰かが楽しく遊んでいると気になりますし一緒に遊びたくなります。
また、自分一人で遊ぶよりも、周りの子どもたちと一緒に遊べる方が子どもにとっても良いストレス発散になる場合があります。(その子の性格にもよるので無理強いはしない)
おすすめの遊び道具・おもちゃ
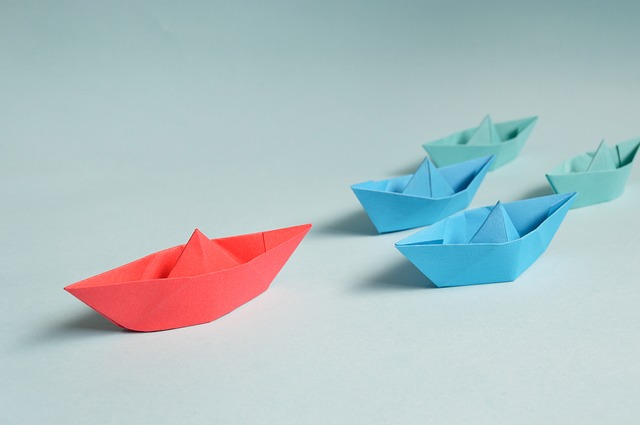
以上を踏まえ、おすすめの遊び道具・おもちゃをご紹介します。他にもたくさんあると思いますが、あんまり思いつかないという方はこの中のいくつかを用意しておくと良いでしょう。
ほとんどの物が100円ショップで手に入るので、手軽で準備しやすいですよ!
昔ながらの、みんなでも遊びやすい物
- おりがみ
誰でも遊んだことがあるので、意外と周りのおばあちゃんとも一緒に遊べることも。折り紙のパッケージの裏に作り方が載っているものもあります。女の子だけでなく男の子も紙飛行機などを作って楽しめます。(飛ばすときは屋外で) - トランプ
トランプもかさばらず、何人でも遊べるのでおススメですが、盛り上がるとつい声が大きくなる事もあるのでその点は注意です。 - ふうせん
避難生活が落ち着いてきたころにおすすめです。遊ぶときは屋外ですが、ボール遊びの代わりに。屋外で遊ぶ場合は、がれきなどがあるため、安全な公園や校庭の片隅で遊びましょう。風船なので人に強く当たりケガをするということが無いのがメリットです。
一人で静かに遊べるもの
- ぬりえ・ノート
集中したらずっと遊んでいるぬりえやお絵かき。最近では大人のぬりえも多くあるので、子一緒に楽しむのもおすすめです。ぬりえもノートもバッグに入るミニサイズにしましょう。個人的には鉛筆削りが必要ないクーピーがおすすめです。(私は折れたクーピーを小さなポーチにまとめて入れています。)
- シール
好きなキャラクターのシールでもいいですし、シールの台紙やセットのシールノートを使って遊べるものもあります。女の子は着せ替えやお買い物を、男の子は乗り物やロボットのシールなど好みに応じて選びましょう。 - スマホ・ゲーム
静かにずっと遊べるものですが、賛否両論あると思います。充電ができる事・予備の電池がある事が前提ですが、画面から目を離しイヤホンをして時間を決めればスマホもゲームもそこまで問題はないかと思います。ワンセグやネット動画で好きなアニメを見るなど、なるだけ日常と同じ事ができるのも大切です。
他にもコンパクトな持ち運びボードゲームやミニパズル、小さなぬいぐるみ、お気に入りのミニカーなど、子どもの好みに応じて準備しましょう。
子どもが何もせずにずっと大人しく静かにすることは難しいです。災害時には精神的にも非常に不安定になるので尚更です。少しでも子どもの緊張や不安を解消してあげられるように心がけましょう。


